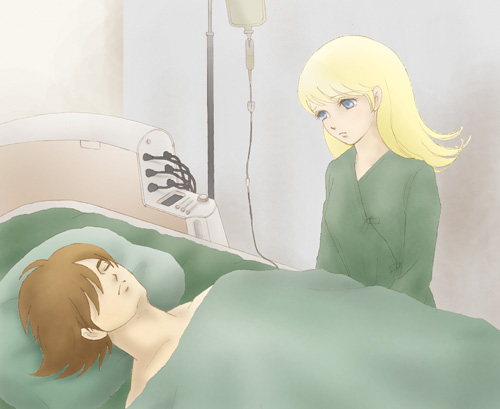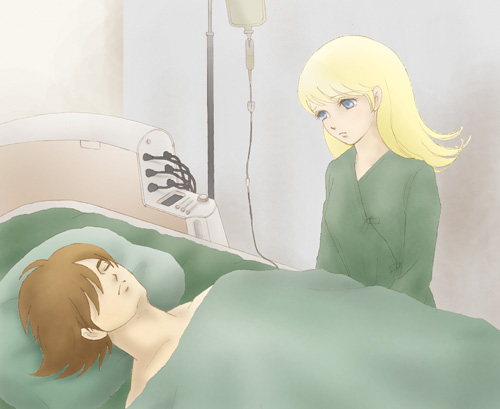
|
written by みさやんさま
|
Everything i do is for you.
〜闇に架ける虹〜
<12>
ギルモア研究所―。
ドルフィン号が緊急帰還してから二時間が経ち、008の補助のもと、009と003の救急治療を終えたギルモアは、グレートが運んできた紅茶を飲みながら、自室で一息ついていた。
そんなギルモアの目の前には、オペを補佐していたピュンマが座っていた。
(普段のギルモア博士ならば、こういう時にはもっと別の表情をしているはずだ…)
ピュンマは、紅茶の香りを楽しむ様子も無く、用意されたものをただ飲んでいるといったギルモアの様子を、ただじっと見つめていた。
ピュンマが座るテーブルには、彼のために用意された紅茶があるのだが、今はそれを飲む気にはなれなかった。
手術中からずっと、気になっている事があったからだ。
やがて、ピュンマの紅茶の湯気が消えた頃、ギルモアがやっと口を開いた。
「ピュンマ、疲れているところ、ご苦労じゃった。君の補佐に感謝している。ドルフィン号での、009の応急処置も完璧じゃった。そのおかげで、009の身体に長時間の負担をかけることなく、手術が捗った。後は、わしだけで大丈夫じゃから、君は皆と共に休んでおいで」
(僕が博士から聞きたいのは、こんな話じゃないのに…)
手術後、深刻な表情で押し黙っていたピュンマだったが、そんなギルモアの言葉に口を開いた。
「…あの、博士」
「なんじゃね?」
「僕は、人体医療には詳しくありません。今回の補佐もやっとでした。ですが、精密機械についてなら、人体用の物でもある程度は解っているつもりです。博士が行った、003に対しての手術なんですが、あれは……」
「そうじゃ彼女はそろそろ…、麻酔が切れる頃じゃな…」
腕時計で時刻を確認したギルモアは、その場に立ち上がった。
「ギルモア博士!」
ピュンマの声が、部屋を出ていこうとしたギルモアを止めた。
「…ピュンマ。オペの最中に、君が知った通りじゃよ」
ギルモアは、ゆっくりとした口調でそう言った。
「博士…」
「わしはこれから、あの子に話をしてくるつもりじゃ」
「そんな…!!何故ですか?!フランソワーズは、今回の戦闘で重要な部分を損傷し、それで003としての機能は使えなくなったということなんですか?!」
「………」
「僕には、そうは見えませんでした!あのオペを見る限り、博士の手によって、使用不可能な状態にしたとしか!」
「その通りじゃ。しかし、それで良いんじゃよ」
「どうして?!もう一度言いますが、僕が思うように、目立った損傷は無かったはずですよね?!」
「いかにも」
「では、視力を調整する器官の一部のパーツを交換すれば、彼女は003として元の状態に戻ったはずです!!」
「つまり、その必要が無かったからじゃ。いや、正確には、その必要は、無くなった。今後、あの子が003である必要はない!」
「それは…、どういうことですか?」
コンコンという、ノックの音と共に、部屋の扉が開く音に振り返ったピュンマは、紅茶のお代わりを持って部屋へと入ってきたグレートと視線が合った。
「ピュンマ、そこから先は、我輩が話すよ。ギルモア博士は、術後の二人の容態を見てくる必要があるからね」
「グレート?」
グレートは、すべての事情を知っているといった表情で、ピュンマを見ていた。
「…すまんな、グレート。それからピュンマ、誤解せんでくれ。状況が急転しての。これは、今後のあの子のためを思ってのことなんじゃ。君が知っての通り、わしは、あの子の視聴覚を、人間としての通常の視聴覚レベルに設定した。無理な使用がない分、パーツの劣化も無く、今後は永久に使用できる」
「ギルモア博士…、それは……」
「グレート、後は頼むよ…」
「あ、博士!!」
自室にピュンマとグレートを残したままギルモアは、診察室を通りぬけた奥の部屋へと向かった。
そして部屋の扉をノックすると、室内へと入った。
その部屋では、今だ麻酔から覚めないジョーとフランソワーズが、ベッドで眠っていた。
もう一度、腕時計で時刻を確認したギルモアは、ジョーが寝ているベッドへと移動すると、ベッドの脇に置かれた医療パネルの中に弾き出されている、各器官のデーターを確認した。
帰還した当初009は、足の傷からかなりの量の血液がもれてしまっていた。
ドルフィン号内で、008が応急処置をしたのだが、さすがに血圧調整器の細部までは修理が出来ず、研究所へと帰った頃には、009の脳内人口血液量は危険な状態だった。
ギルモアは、ジョーの体内に取り付けた新しい血圧調整器が上手く稼動し、体内の各器官の機能が、正常値へと回復したことに安心した。
(009は、一時間以内には覚醒するだろう…)
「博士?…ですか?」
データーパネルを診るギルモアに、麻酔から目覚めたばかりのフランソワーズが声をかけた。
その声にギルモアは、二つのベッドの間のカーテンを、部屋の半分くらいまでひくと、フランソワーズのベッドの脇へと立った。
「フランソワーズ、目が覚めたかね」
「…はい」
「大変な環境での戦闘だったようじゃな。全員、無事に帰ってきてくれて、ほんとに安心したよ」
ギルモアは、心底ほっとした笑顔で微笑んだ。
フランソワーズは、ベッドから起き上がると、視線をジョーのベッドへと移した。
「…あの、ジョーの容態は?」
「もう心配せんでも大丈夫じゃ」
「大量に出血していたようなんです…」
「分かっているよ。術後、各器官に異常は無いしバイタルサインも安定しておる。今はまだ麻酔の関係で眠っておるが、あと一時間以内には、目覚めるじゃろう」
「…良かった」
フランソワーズは、笑顔を見せた。
「君の具合はどうじゃね?」
「少し、頭が重い気がします」
「麻酔がまだ残っておるようじゃな。頭痛や吐き気はあるかね?」
「どちらも、ありません」
「そうか」
術後の体調が良好な事に安堵したギルモアは、白衣のポケットから白い封筒を取り出していた。
「博士、イワンはどうしているのかしら?」
「ああ、イワンなら疲れて寝ている。実は、君達と連絡が取れなくなってから、あの子なりの方法で、探しておったようなんじゃ」
「こんな遠くからイワンが?」
「詳しいことは、本人に聞かんと分からんのだが、負傷した009の状態をわしに告げた瞬間、眠ってしまってな。イワンも、力になりたかったんじゃろう。イワンが眠ってすぐに、ドルフィン号とも連絡がとれての。それで敏速に、ピュンマに緊急処置の指示を伝えられたんじゃ」
「そうだったの、イワン」
「………」ギルモアは、渡すタイミングを逃した封筒へとふと視線を落とした。
「博士」
「…なんじゃね?」
「その封筒は、なんですか?」
フランソワーズは、少し前からギルモアが手に握ったままの封筒を気にしてそう尋ねた。
「ああ…これなんじゃが…。フランソワーズ、実は…、これから君にとって個人的に重要な話がある」
「…話し?」
フランソワーズは、重要な話しと聞き、ふと不安げな表情を見せた。
「なにぶん急なものでの…」
そう言いながらギルモアは、フランソワーズに白い封筒を渡した。
「心配せんでも大丈夫じゃよ。これは、良い知らせじゃ。開けてみなさい」
「良い、知らせ…」
受け取った封筒を不思議そうに眺めていたフランソワーズだが、やがて封を開いた。
封筒の中には、折られた一枚の紙と、シルバーのネックレスが入っていた。
フランソワーズは、見覚えのあるそのネックレスを見て驚いた。
見覚えのあるそのネックレスは、個人認識のために身に着ける物で、呼称、ドッグタグと呼ばれるものだったのだが、
そしてそのプレートにはJean Arnould. と掘り込まれていたからだ。
「…これは、兄さんの……」
フランソワーズは、封筒の中に一緒に入っていた折りたたまれた紙の方を、急いで開いた。
そこには、懐かしい兄の文字で、パリの住所、それから日本のホテルの名前と部屋番号、最後に日付とサインが書かれており、兄の物であろう名刺も挟まれていた。
その名刺は、フランスの有名な航空会社のものである。
今の兄は、この会社で航空機のパイロットをしているということだろうか?
そして便箋に書かれた日付、兄はこのホテルにいるのだろうか?
「あの…いったい、…これは」
言葉に詰まったフランソワーズは、驚きのあまり目を見開いてギルモアを見た。
「実は先日、とある偶然から、君のお兄さんが、この研究所を訪ねて来ての」
「…博士、あの…、今、なんて…、ほんとに、兄が…」
「ジャン・アルヌールさんは、今は、民間機のパイロットをしておるそうでの、そしてずっと、君の事を探していたそうじゃ…」
「ずっと…、私を探して……」
「…わしは、君のお兄さんが此処に訪ねてきた時、君の身に起きたことを、君のお兄さんに話した」
「あの…、では兄は、私の身体の事を…」
「今は知っているよ」
「…………。そうですか…」
ギルモアの言葉にフランソワーズは、不安と喜びが入り混じった、なんとも複雑な表情で封筒を眺めていた。
「だがフランソワーズ、君が心配しているような事は、無いはずじゃよ。安心しなさい」
彼女の心の内を見抜いたような、ギルモアの言葉だった。
フランソワーズは、自然と涙を流していた。
「…兄さん…」
「さっそくじゃが明日、お兄さんに会ってはどうかね?君がここに帰ってきたことは、実はすでに連絡してある。すぐにでも君に会いに来たいと仰っていたのじゃが、帰還時の君達の状況を話したら解って下さっての。落ち着いたら、連絡が欲しいとのことじゃ。…フランソワーズや、お兄さんのことじゃが、ほんとに良かったのう」
「…博士」
シーツが、次々に涙を吸い取っていく様子を見てギルモアは、白衣からハンカチを取り出すと、それを渡した。
「…ありがとう。なんとも言えない気持ちだわ。しばらく、涙が止まりそうにない…」
そんなフランソワーズを見てギルモアは、
(術後ということもあるが…、精神状態を考えても、今は、ここまでを話すので精一杯じゃな…。…耳と眼の手術の事は、明朝、伝えることにしよう…)と内心思った。
「しばらくは、まだここで休んでいなさい。おお、そうじゃ!009が目覚めたら、知らせてくれるかの?」
「ええ、…分かりました」
ギルモアは、いささか不安が残る表情で自分を見つめるフランソワーズにそう言い残すと、部屋を出た。
***
医療機器の音だけが聞こえる静かな病室で、ベッドから立ち上がったフランソワーズは、ジョーのベッド脇のパネルに映しだされているバイタルサインを確認すると、傍に置いてあった椅子へ座った。
そして、壁にかけてある時計で時刻を確認したフランソワーズは、まだ麻酔から目覚めないジョーの横顔を、そっと見つめた。