***
そんな大切な場所だったから、僕は仲間の誰にも話さなかった。
誰かと共有するのは恥ずかしかったのと――何故この場所が好きなのかを話す羽目になるし――
何より、自分だけの場所を持っていたかったのだ。
ただひとりを除いて。
いつか、一緒に見に行きたい。あの灯を見せたい。
そう思ってはいたけれど、「いつか」はあまりにも漠然としていて、いったいその「いつか」がいつやってくるのか
さっぱりわからなかった。
「いつか」は偶然やって来るのだろうか。
それとも、永遠にやってこないのだろうか。
買い出しには基本的にひとりで行くようになっていたから、二人で出かける機会を期待することはできない。
もちろん、買い出しに一緒に行って欲しいと言えばいいのだろう。そして帰り道にここに寄って。
それも考えたけれど、すぐに却下した。
なんだか――そう、この思いは「何かのついで」にしたくはなかった。
ちゃんと
「見せたいものがあるから、一緒に行こう」
って言いたかった。
***
そう心に決めてはいたものの、さていつどうやって誘えばいいのだろうか。
何しろギルモア邸には全員が住んでいるのだ。
ミッション直後だったから、順番にメンテナンスを受けることになっていて誰も帰っていない。
メンテナンスを受けた順に帰っていいことになってはいたけれど、それでもみんな残っていた。
だから、うまい具合にフランソワーズとふたりっきりになることもなく、ただ日が過ぎていった。
このままではいけない。
遅ればせながら気がついた。
このままでは、いつまでも誘えないではないか。
そりゃ、僕は今まで数えるくらいしか女性をデートに誘ったことはないけれど、でも全くないわけじゃないんだ。
誘うと決めたら、絶対誘う。
それだけは決めていた。
***
朝ごはんの支度を一緒にするというのはどうだろう?
大抵、朝の支度はフランソワーズがひとりでしているから、キッチンでふたりっきりというのは自然だろう。
――よし。
僕は前の日から固く決意してキッチンに降りて行った。
午前7時。
「おはよう、ふら――」
言いながら入ってゆくと、そこには。
「あらジョー、おはよう。早いのね」
「おう、今日は早いな。どうした」
「雨でも降るんじゃねーの?」
三組の瞳に迎えられた。
――なんで。
「どうしてここにいるんだ」
「うん?朝メシの準備。マドモアゼルだけにさせておくといつも同じメニューだからな」
「まあ!酷いわ、ハインリヒ」
「そうそ、俺様は朝からがっちり食いたいんだ」
「朝からハンバーガーなんてバカじゃないの」
「うるせーな、いいんだよ」
ハインリヒとジェットだった。
僕は思い切り脱力して、ただただそこに突っ立っていた。
何か手伝えといわれたような気もするけれど――何もする気が起きなかった。
***
僕は朝ごはんを食べながら考えた。
そう――ものは考えようだ。
「明日一緒に出かけないかい?」と言うのは、午後のほうがいい。
朝に誘って、「考えておくわ」なんていわれた日には、今日いちにちずっと悶々として過ごすだろう。
だけど午後だったら、その苦しみは半分になるし、そんなに畏まったデートの誘いってわけでもないから、
時間に猶予がないほうがフランソワーズだって「そうね」って軽く答えてくれるだろう。
よし、決めたぞ。
昼ごはんの後だ。
まだ朝ごはんの途中だというのに、僕の心は今日の午後に向いていた。
どんなシチュエーションでフランソワーズをつかまえ、そして誘うのか。
軽く言ったほうがいいのか、あるいはちゃんと「デート」なのだとわかるように言ったほうがいいのか。
思えば、相手が外国人というのは初めてだった。
――そういえば、ジェットが言ってたな。
俺たちは日本人じゃねーから、婉曲した表現とやらがわからねーし、謙譲の美徳ってやつもわからねえ。
大体、「察する」文化はまだるっこしいんだよ。言いたいことがあるなら最後まで言え。
語尾をあやふやにされたらどうしたいのかさっぱりわからねえ。
たぶん――フランソワーズも同じなんだろうな。
だとすれば、「ちょっと出かけない?」っていうのはきっと駄目だろう。
そこらへんまでちょっとお使いにっていう意味にとられかねない。
そうじゃないんだ。
僕は、フランソワーズとふたりっきりであの景色を見て、そして――ともかく二人でいたいんだ。
たくさん話をして、フランソワーズの声を考えを聞いて、どんな女の子なのかもっともっと知りたい。
それには、数分じゃなくて数時間一緒に居なければ駄目だ。
そんな短い時間じゃ全然足りない。
でも。
だからといって「僕とずうっと一緒に過ごさない?」って言ったら、今度は変な意味にとられてしまうかもしれない。
いや、僕はそれでもいいんだけど――
――イヤ、駄目だ。
いやそうでもないかな?
だってフランソワーズとその・・・朝まで一緒っていうのは楽しそうだし、その、文字通りそういう意味にとられて
そうなってしまうのも自然の流れというか何というか――で。
男としての僕は、それもいいなあとつい頭のなかでモヤモヤ考えてしまった。
だから、きっぱりとした涼やかな声で問われた時はびっくりした。
「ジョーったら!」
「あっ、はいっなんでしょう」
背筋が伸びる。
まるで頭の中を見られたかのような妙な気分だった。
フランソワーズには頭のなかも見えるのかな?
――そうでないことを祈る。
「ジョー?どうしたの?」
「えっ?」
「さっきから手が止まってるわよ」
笑いを含んだ声で言われ、僕ははっとして周りを見た。
みんなが僕に注目している。
「え・・・と」
そうだった。まだ朝ごはんの途中だった。
僕は魔法が解けたように手を動かし、箸でつかんだままの卵焼きを口に放り込んだ。
「ジョー。おかわりは?」
「えっ」
「お茶碗がからっぽよ?」
「――あ」
いつの間にか、茶碗が空になっていた。
「おかわり、するんでしょう?いつも二膳は食べるものね?」
フランソワーズが腰を浮かす。右手を僕のほうに伸ばして。
「おかわり――ウン」
茶碗を渡せば、フランソワーズはそれにゴハンをよそってくれるのだろう。いつもそうだ。
僕は、こちらに伸ばされた白い指先を見つめ、箸を置いた。
そして茶碗を渡した。
渡したつもりだった。
でも僕がしたのは、フランソワーズの手を掴むことだった。
――あれ?
「あの・・・ジョー?」
フランソワーズが困ったように僕を見る。
蒼い瞳。
その瞬間、僕の口は勝手に動いていた。
「フランソワーズ。明日、一緒に出かけないかい?二人だけで」
フランソワーズが目を丸くする。
「えっ・・・」
「駄目かな?」
「だ、駄目じゃ・・・ない、ケド」
「良かった」
フランソワーズが手を引こうと身じろぎしたけれど、僕の手は彼女の手を離す気はないようだった。
「おいおい、お前ら、いちゃいちゃするなら他でやってくれ」
「そうそう、邪魔邪魔。そこの醤油が取れないじゃないか」
「明日はデートか。いいねぇ、若いもんは」
「い、いちゃいちゃなんかしてないわ!」
フランソワーズが思い切り僕の手を振り切った。あっけなく離れる手と手。
「別に、一緒に出かけるだけでしょう?そうよね、ジョー」
「うん」
「そんな冷やかされるようなことじゃないわ!」
つんと顔を背けるとフランソワーズは僕の茶碗を奪い取ってキッチンに消えた。
「ジョーよ。マドモアゼルはああ言ってますが?」
「デートじゃねーのかよ」
「さあ・・・どうなんだろう?」
どうなんだろう?
その答えはきっと、おかわりしたごはんと一緒にやってくる。
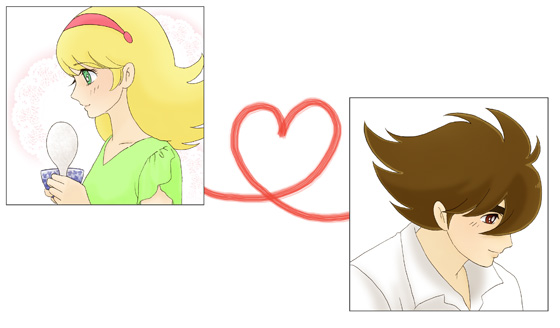
2010.7.30
Presented by うさうささま
Special Thanks!!
うさうささま素敵サイト「Grande valse brillante」さまはコチラ☆

|