|
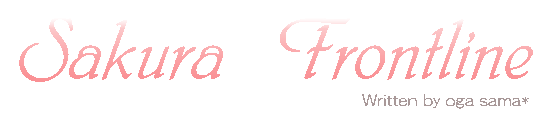
【1】
「そろそろ行ったほうがいいのかしら・・・。」
彼の横顔を見上げるようにして、彼女が静かにささやいた。
桜の枝が描くアラベスク文様を透かして、空を見上げていた彼は、深呼吸をひとつして
「まだ居たいけど・・・もう行かなきゃならないだろうね。」
と名残惜しそうに微笑んだ。彼の視線の先には、開いたばかりの桜の花が薄紅色に明るんでいる。
彼女が立ちあがったとき、吹き抜けた海風に白いスカートがなびいた。
「それじゃ・・・ね。」
さっきまで背中を持たせかけていた桜の幹に手を当て、別れの挨拶を送る。
振り向くと、もう彼はアクアマリンの空を背にして、地面を離れていた。軽く助走をつけるようにステップを踏むと、
ふわりと体が浮く。
彼女を抱きとめた彼は、腕に彼女を抱いたまま、ゆっくりと桜の樹から離れて行った。
枝の先にまだ遠慮がちに花を開かせたばかりの桜は、やがて春の陽の中で絢爛の満開を迎え、豪奢な花吹雪を
舞わせることだろう。
だが、自分たちにそれを見ることはかなわない。
「元気でな・・・。」
彼の声が湿りを帯びているのに気づいた彼女は、
『あなたも寂しいのね・・・。』
そっと彼の胸に頬を寄せた。
そんな彼女を愛しげに見つめ、亜麻色の髪に軽く口づけを落とした彼は、心を決めたようにきっぱりと言った。
「行こう。」
これから向かう空を見上げる。
「どのくらい、行くの?」
「そんなにはかからないと思うよ。・・・しっかりつかまってて。」
彼は高度を上げはじめた。桜の樹が見えなくなっても彼はぐんぐん高度を上げた。スピードもどんどん早まる。
やがて彼は、上昇するのを止めた。
遥か足元に蒼い曲線が輝いている。
空の紺青が色を深めて頭上の漆黒へと移ろうここは・・・成層圏。
この高さに至ってさえ寒さも息苦しさも感じることがないのは、自分たちが人外の存在だからなのだろう。
彼が眼下を遥かに指し示した。
「ごらん・・・ボクたちはあの風をつかまえるんだ。子午線にそって北へ3度・・・それから東へ6度・・・。」
ふたりはしっかりと手をつなぎあうと、勢いよく下降し、気流を捉えた。
「速い!・・・とっても速いわ!」
彼女の空色の瞳が輝く。
「うまく高気圧の吹き出しに乗れたからねぇ・・・キミってスピード狂なんだ?」
いたずらっぽく煌めく明るい茶色の瞳に、彼女は茶目っ気たっぷりに言った。
「いやなジョー・・・そんなに言うなら、捕まえてごらんなさい。」
彼の手をするりと抜け出す。
「言ったな!フランソワーズ!」
明るく言い返す彼の声を置き去りにして、彼女はスピードを上げた。
『うふふ・・・』
目の下に広がる海はどこまでも青かった。穏やかにうねる波の頂きぎりぎりまで降下し、手のひらでぱちゃぱちゃと
波頭を跳ね上げる。空に放たれた雫がきらきらと光る。
思いもかけない水しぶきにカモメがあわてて飛び立つ。
白い翼と白いワンピースがしばし並んで飛翔し、鮮やかな飛跡を描いて彼女がカモメを追い越した。
「ぁん!」
不意に腕を掴まれて、彼女は小さな悲鳴をあげた。
「つかまえた!・・・この、おてんば娘!」
誇らしげな彼の微笑みに、彼女が可憐に頬をふくらませる。
「ほら、クルーズ船だよ。」
彼が指差した方向には白い客船が海を行く姿があった。
「行ってみよう。」
船上では賑やかな結婚パーティーが開かれていた。新郎新婦の脇を彼がすり抜けたとき、彼が起こした風に花嫁の
ヴェールが高くなびいた。
「ごめんよ!」
あわてて花嫁のヴェールに手を添える花婿に、彼はまったく悪びれていない風のお詫びの言葉をかける。
「ん、もう・・・あなたは・・・!」
彼女にやさしくにらまれた彼は
「さっきはごめん・・・」
今度はしおらしく謝りながら、花嫁のブーケに手をかざした。
固く巻いていたバラのつぼみがふわりと緩み、白い花で作られたブーケの中、淡いピンク色の花びらが微笑む。
ブーケに仕込まれた趣向だと思ったのだろう、花嫁がはしゃいで花婿にブーケを見せている。
「お幸せにね。」
ふたりは花嫁に微笑みかけると、何かを確かめ合うように互いに頷き合った。
「行こう。・・・もうすぐそこだ。」
目的地はそこからすぐの場所だった。
ゆっくりと地面に降り立ったふたりが、手を取り合って見上げたそれは、まだ蕾の固い桜の老木だった。
「おお・・・よう来たの、二人とも。」
幹の陰から、小粋な蝶ネクタイの洋装に白いひげをたくわえた老人が現れた。
「早過ぎましたか?」
「なんの・・・なに、少々チェスに興じていたのでな・・・。」
「それではボクらは仕事にかかります。」
"それなんじゃがの・・・"と老人は言いにくそうに口篭もった。そのとき、
「まだ"待った"は終わらないのかね?」
別の老人が"ほっほっほっ・・・"と楽しそうに笑いながら姿をあらわした。この老人は洋装の老人よりは少し小柄で、
黒い和服を着流しにしていた。礼儀正しく挨拶しようとする二人を身振りで制し
「そう急くこともあるまい。・・・見物して行きなさい。なに、あともう一手二手で勝負がつくからの。」
「なんじゃと・・・。」
気色ばむ洋装の老人をかるくいなした着流しの老人は、背中を向けたまま右手をひらひらと振り、幹の向こうに回って
いった。
桜の幹の裏側には緋色の毛氈が引いてあり、酒肴の用意とチェッカーボードがしつらえてあった。
『碁盤でも置いてある方がふさわしいな・・・』
と彼が見ているうちに、和服の老人の鮮やかな一手で勝負が決した。洋装の老人が、苦虫をかみつぶしたような顔で
「ワシの負けじゃ・・・」
とさして悔しそうでもない口調で言う。
「されば・・・じゃ。」
和服の老人は、懐から小指ほどの桜の枝先を取り出した。
「先の季節外れの雪で枝から離れてしもうての・・・せっかく花芽を抱いておるものを、不憫だと思うたのじゃが、この
唐変木めが・・・。」
洋装の老人に向かって、わざと恨めしそうな顔を作る。
「それが自然の摂理というものじゃよ。・・・天の与えたもうた試練に耐えきれぬものが落ちてゆくのはいたしかたのな
いことじゃ。」
「あ・・・だから・・・チェスを?」
ジョーが気がついたように言う。
"ほっほっほっ・・・"と和服の老人が
「お前さんたちの最初の仕事じゃよ。」
手にした桜の枝先をフランソワーズに差し出した。
彼女はスカートをつまんで右足を引き、小さく会釈をしてそれを受け取った。ジョーが彼女の肩を抱き寄せ、桜に向か
って手をかざす。
固く閉じられていた花芽が柔らかく膨らみ赤みを増したかとみるや、淡く紅を帯びた五弁の花びらが開く。
フランソワーズがジョーを見上げてにっこりと微笑み、すぐに
「でも・・・この花は命をつなぐことはできないのね・・・。」
涙ぐんだ。"ア・・・"と茶色い瞳を見開いた彼は
「・・・泣くな、フランソワーズ。」
小さなキスで彼女の涙を拭う。
「ボクらが憶えていてあげよう・・・」
心をこめた深い声で囁き、優しく彼女にキスをする。
「若いモンはいいの・・・。」
洋装の老人が目を細めた。
「この木くらいは咲かせてやってはどうかね?・・・本来あの子たちには決して見ることは許されんのだから。」
和服の老人が面白そうに答える。
「ほう・・・お前さんがこんなことを言うとはな・・・。」
「自然の摂理を曲げたんじゃ。・・・曲げついでというところじゃよ。これであの娘の涙も乾くじゃろうて。」
「それなら・・・この年寄りもいいところを見せようかの・・・。」
和服の老人は、桜の老木の幹をコツコツ、と拳でノックした。
ざわっ・・・
風もないのに、まるで風に吹かれたように枝が揺れ、みるみる蕾が膨らんだ。
あどけなく笑う二分咲きから
若々しく微笑む五分咲きに
そして・・・威風あたりを払う満開へ
わずかな時の間に爛漫の春を描き出した桜は、この地に根を下ろしてからの星霜を思い返しているかのようでもあっ
た。
洋装の老人は少し離れたところから、満開の桜とそっと寄り添っている恋人たちを眺め、ふわりと目元を緩めた。
年年時を同じくして花は咲き、花は散る。
しかし、その花とてひとつとして同じ花はなく、それを眺めるものもまた、同じではない。
ギリシアの哲学者はそれを万物流転と看破し、イスラムの詩人はなんというむなしさかと詠じた。
万物には天に定められた時があり、万物の動きは時の理にかなっている。
植えるに時があり、植えたものを抜くに時がある。
愛するに時があり、憎むに時がある。
生まれるに時があり・・・死ぬに時がある。
ものみな等しく唯一無二の存在として時の理のなかで精一杯に生きているからこそ、この世はかくも美しく・・・愛しい。
「お前さんがそんなに優しく笑うとは・・・天地がひっくり返るぞい。」
「ワシが笑ったくらいでひっくり返るような天地なら、もうとうの昔にひっくりかえっておるわ。のう・・・南の。花が咲き実
を結ぶ・・・花は因、実は果。われらが司る自然の摂理ももとまで遡れば因果の律にたどり着く。因果の間を繋ぐのは
縁というヤツじゃが、因果の間で縁を生むのは、お前さんのいうとおり・・・愛というものなんじゃろうな。」
和服の老人は"お前さんにしては・・・"という得意の台詞を呑み込んだ。
「そうじゃろうとも・・・時の風が吹きすさぼうとも、愛だけは永遠に・・・。」
自然の摂理の番人にして命あるものの生と死を司る南と北の老人は、懐かしく、切なく、甘い想いが心にひたひたと
満ちて来るのに任せていた。
ほどなく、和服姿の南の老人が物思いを振り払うように、しゃんしゃん、と華やかに手を打った。
「さあさ、お二人さん。仕事にかかっておくれ。・・・今年は前にも増して、賑々しくやってもらおうよ。」
【2】
「・・・ズ。フラン・・・ワーズ。大丈夫?」
「ジョー?」
自分をのぞき込む明るい茶色の瞳を見返すと同時に、フランソワーズは自分の置かれた状況を理解していた。
落盤事故に見せかけて敵の地下プラントを爆破するための任務についていたのだ。爆破工作にあたるのはジョーで、
自分は彼を援護するための索敵にあたっていた。爆破直前に、彼の加速装置を使って脱出・・・という手順になっていた
はずなのだが、"ここ"は、当初計画していた退避場所ではない。
『黒い幽霊団』の偽装活動によって廃棄させられたのだろう、廃屋が点在する小さな村落のアーモンド畑の中に建つ、
壊れた石造りの建物の陰だった。
『シークェンスは?』
素早く周囲をサーベイする。敵プラントは落下した岩盤の下だ。誘爆の轟音も止まっているから、任務は終了したと判断
していいだろう。フランソワーズはほっと安心したように吐息をおとした。
「誰も見る人がいないのに・・・きれい・・・。」
「年年歳歳花相似 歳歳年年人不同」
ジョーが詩のようなものを口にした。
「人間が愚かな争いを繰り返していても・・・花は変わらずに咲くんだな・・・」
「ええ・・・世界はこんなに美しいのに・・・なぜ人は争うのかしら・・・。」
フランソワーズの空色の瞳が潤みを帯びているのに気付いたジョーは
「キミに謝らなきゃならないことがあるんだけど・・・」
彼女の気持ちを引き立てるようにおどけた調子で言った。
「・・・計算ミスしたみたいでさ、爆発が想定より早くなっちゃったんだ。」
いたずらがバレて叱られた子供のような口調で"ごめんなさい"を言う009に、フランソワーズはまるで、彼を叱っている
母親のような気分になった。
「もうこんなこと、しちゃだめよ。・・・めっ。」
ジョーの額に自分の額をこつん、と触れさせて言った後、彼の頬にこびりついた煤を指先で拭いながら
「でもあなた、謝ってばかりね?」
と続けた。
「え・・・?ボクが・・・?」
「ちがうのよ。夢のお話。・・・あたしね、夢を見ていたの。あなたと・・・一緒に空を飛ぶ夢。」
「そこでボクが、謝ってるわけ?」
"何かした?"と真剣に考え込む目つきに、フランソワーズは彼女の夢の話をした。
ジョーと一緒に桜の花を眺めていたこと
ジョーには、不思議な力があったこと
不思議なおじいさんに会って、そして・・・
「あながち・・・夢とばかりは・・・。」
ジョーはふわりと目元をゆるめ、フラソワーズの傍らから、ちいさな桜の枝を拾い上げた。それは、"この場"にはあるはず
のないものだった。
「キミの夢の中でボクは、こうしてはいなかった?」
彼女の肩を抱き寄せるとジョーは、桜の枝に手をかざした。
「現実のボクに花を咲かせる力はないけど、この枝を培養して命をつなぐ技術の力はある・・・。」
「それじゃ、あなたも・・・?」
フランソワーズの問いには直接答えずに、ジョーは
「そういえば、あのおじいさんたち・・・ギルモア博士とコズミ博士にそっくりだったよなぁ・・・。」
彼女の肩を抱いたまま、のんびりとした口調で言った。
何かに気付いた彼女が、頬を染めて俯く。
「やだ・・・あたしたち・・・。」
「博士たちの前で、こんなことしたの思い出した?」
いたずらっぽく茶色い瞳を煌めかせたジョーは、くい、と彼女の頤に指をかけ、自分の方を向かせた。フランソワーズは
瞳を閉じて、彼のキスを待った。
・・・が、落ちて来たのは、彼の唇ではなく、小さな溜息だった。
瞳を開いた彼女に向かって、ジョーは困ったような顔で、こめかみの辺りをちょんちょんと指でつついた。脳波通信の回路
を開くと、ジョーが仲間たちと内線通話(しゃべ)っている内容が飛び込んで来た。
―――無事だ・・・003もモチロン一緒だ。
これはドルフィン号でオペレーションコントロールにあたっているピュンマとの会話だ。
―――誰に向かって口きいてんだよ!ケガなんかさせるかよっ!・・・俺の女だぞっ!
こんな口をきく相手は、"不良仲間"のジェットしかありえない。
―――ミッションは成功・・・ピュンマ、ボクらの座標は拾えた?・・・ピックアップ頼むよ。
「もう切っちゃおう・・・エマージェンシー回線も閉めちゃえ。」
"そんなことしていいの?"と彼女が訊くより早く、ジョーの脳波通信が切れた。
―――そんなに一度に話しかけられたら、チャンネルがパンクしちゃうよ!
だだっ子が投げつけたような脳波通信を最後に、ジョーの回線が沈黙した。
ドルフィン号のコックピットでは004ことアルベルトが肩をすくめ
「009のヤツ、エマージェンシーラインまで切っちまうとは・・・呼ぶか?」
誰にともなく言った。
エマージェンシー回線はパッシブ回線である。たとえ009が回路を閉じていても、誰かがこの回線を使って呼びかければ
自動的に回路がつながり回線が開くのだ。
「座標はわかるから放っておいてかまわないよ。」
ジョーのかわりに操縦桿を握るピュンマが答える。
「そろそろ映像が出るんじゃないか?」
コンソールパネルに腕を伸ばしたのはピュンマのかわりに副操縦席に陣取るグレートである。
メインスクリーンに出力された映像はコックピトにいた全員を絶句させ・・・
「なにが、ボクたちはべつにぃ・・・だ!」
「私服を投下してさっさと帰投しようぜ。・・・歩いて帰りゃいいだろ。」
大ブーイングの嵐を巻き起こした。口々に勝手なことを言い合う"若い連中"を尻目に
「古人無復洛城東 今人還対落花風・・・若さを楽しませてやりましょうや、博士。」
泥鰌髭をひねりながら張大人が漢詩を詠じ、ギルモア博士に笑いかける。
ドルフィン号のメインスクリーン―――超高解像度ディスプレイは、春の夕刻、淡いピンク色の花を枝いっぱいにつけた
満開のアーモンドを背に、熱いキスを交わしている恋人たちの姿を克明に映し出していた。
|

